相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
(論点)相続登記と相続税における不動産評価額の違いとは?

相続が発生した際、不動産を引き継ぐには相続登記が必要となります。その際、「登録免許税」が発生しますが、その課税標準となるのは「固定資産税評価額」です。一方、相続税の計算では異なる評価方法が適用され、結果として異なる評価額が算出されます。本記事では、相続登記と相続税における不動産評価額の違いを詳しく解説し、それぞれの評価基準や計算方法についてご紹介します。
目次
- 相続登記の登録免許税における不動産評価額
- 相続税の計算における不動産評価額
- 固定資産税評価額と相続税評価額の違い
- 実務における影響
- まとめ
1. 相続登記の登録免許税における不動産評価額

相続登記を行う際に納める「登録免許税」は、不動産の「固定資産税評価額」を基準として計算されます。
固定資産税評価額とは?
- 各市町村が毎年1月1日時点の評価額を基に算定。
- 固定資産税課税明細書や固定資産評価証明書で確認可能。
- 市場価格より低めに評価されることが多い。
登録免許税の計算方法
- 課税標準額(固定資産税評価額)× 0.4%(相続登記の場合)
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は 4万円(1,000万円 × 0.4%) となります。
2. 相続税の計算における不動産評価額
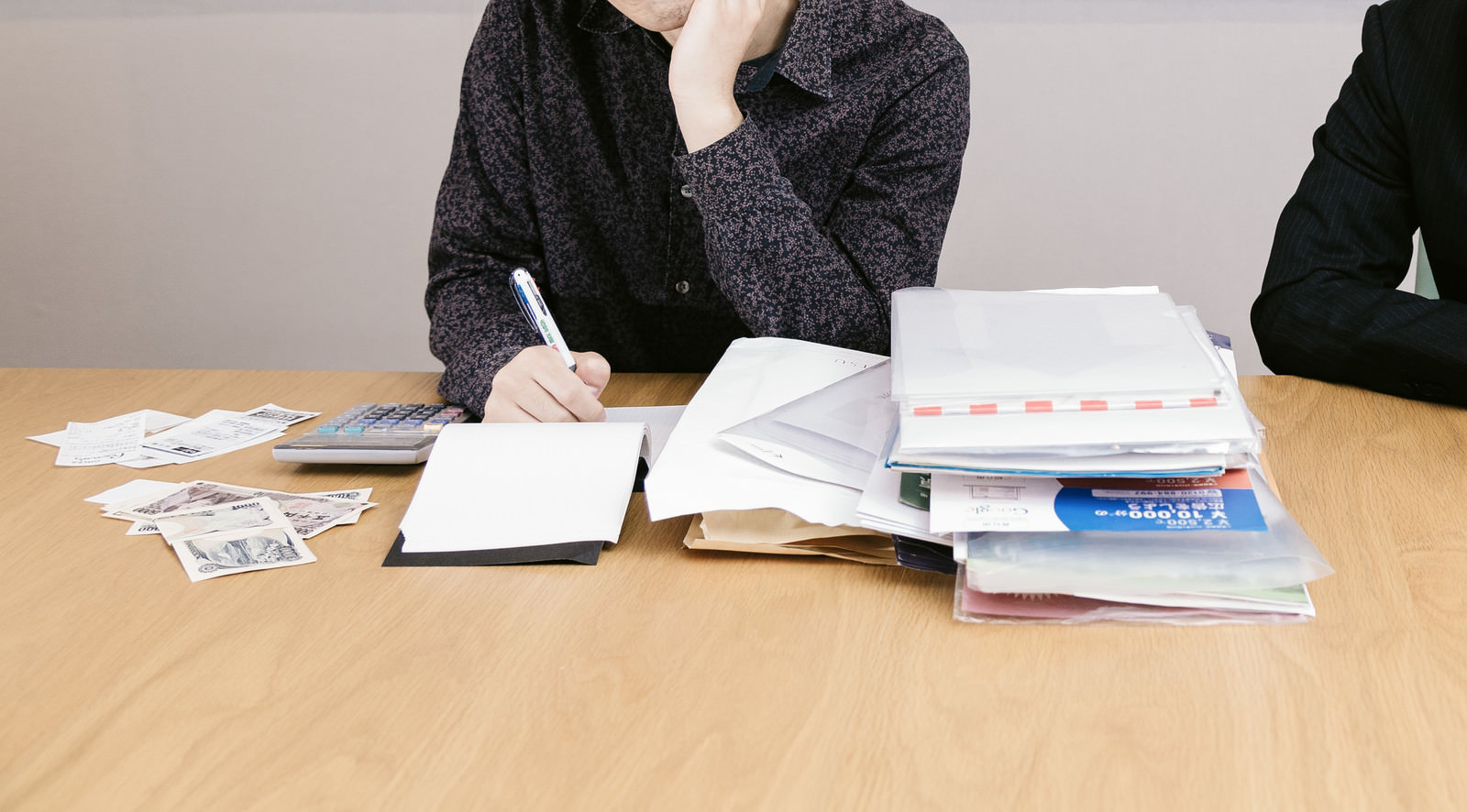
相続税を計算する際の不動産評価額は、国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて決められます。
(1) 路線価方式(市街地の土地)
- 国税庁が定める**路線価(1㎡あたりの価格)**を基に評価。
- 計算式:土地の面積 × 路線価 × 補正率
- 市場価格の約80%程度になることが多い。
(2) 倍率方式(郊外の土地)
- 固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて算出。
- 計算式:固定資産税評価額 × 倍率
(3) 建物の評価
- 建物は固定資産税評価額をそのまま使用。
- 土地と異なり、固定資産税評価額=相続税評価額となる。
3. 固定資産税評価額と相続税評価額の違い

4. 実務における影響
(1) 登録免許税の計算は相続税評価額より低め
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額を基準とするため、市場価格や相続税評価額よりも低く算定されることが多いです。
(2) 相続税の評価額は固定資産税評価額より高くなる傾向
特に市街地の土地の場合、固定資産税評価額よりも高い路線価が使われるため、相続税評価額が高くなりやすいです。
(3) 節税対策のポイント
- 小規模宅地等の特例を活用すれば、相続税評価額を最大80%減額できる可能性あり。
- 土地の分筆や利用方法の変更で評価額を抑えることも検討。
5. まとめ
相続登記の際の登録免許税の課税標準は「固定資産税評価額」、一方で相続税の計算には「相続税評価額」が用いられます。土地の評価方法として、相続税では「路線価方式」や「倍率方式」が適用されるため、相続税評価額のほうが高くなることが一般的です。
そのため、相続登記時の税負担は比較的軽いものの、相続税を計算する際は慎重に評価方法を確認し、節税対策を検討することが重要です。特に、相続税の負担を抑えるためには、小規模宅地の特例の活用や評価額を下げるための工夫が有効となります。
相続に関する税金は複雑なため、具体的なケースについては専門家に相談することをおすすめします。

最新のブログ記事
【第5回】 繰り返しが記憶を支える ― 回すスケジュールの立て方
司法書士試験において、記憶の定着は"時間"ではなく"回数"で決まります。
どれだけ時間をかけても、思い出す訓練をしなければ記憶は長続きしません。
本記事では、年明けから直前期にかけて「一週間で全科目を回す」ためのスケジュール設計と、朝夜の使い分け、復習タイミングの最適化方法を詳しく解説します。
橋本式「回す学習法」を形にする最終ステップです。
嫌われることは、人生の失敗ではない ― 50歳で司法書士を目指して気づいた「人間関係の真実」
多くの人は「嫌われること」を極端に恐れます。しかし50歳を過ぎ、司法書士試験という人生最大の挑戦をした私は、嫌われることはほとんど問題ではないと気づきました。むしろ、人の目を気にして自分の人生を止めることのほうが、はるかに大きな損失だったのです。挑戦すると人は離れ、否定され、時には傷つけられます。ですがそれは、あなたが間違っている証拠ではなく、「本気で生き始めた証拠」なのです。
ここまで4回の記事で、
**「不動産 × 認知症 × 義務化」**がどれほど危険かをお伝えしてきました。
しかし本当に大切なのは、あなたの家が今どの状態なのかです。
結論から言えば、ひとつでも危険サインがあれば、すでに対策が必要な段階です。
このチェックリストで、あなたの不動産が「守られているか」「爆弾になりかけているか」を確認してください。



